|
|
|
|
岡山NPOセンター |
|
|
|
|
|
2026/1/19 |
| 第 1 回 顧 問 会 議 |
| オ ン ラ イ ン で 意 見 交 換 |
| -NPOで働く人の会- |
岡山県内ボランティア団体の中枢的活動を展開している特定非営利活動法人岡山NPOセンターの顧問会議が1月19日夜、オンラインで行われました。
冒頭、同センターの高平亮代表理事が「本年度は支援者支援について青山織衣氏のご協力を得て事業の枠組みを整えることができました。会員拡大はこれから検討する重要なことと考えています」と報告を兼ねて挨拶。
この日は互助的ネットワーク「NPOで働く人の会」への期待や、会員獲得へ向けて取り組めそうなプランを中心に意見交換が行われ、出席者からは広報紙やSNSなどを活用したアイデアが出されました。次回開催日は1月30日。
YouTube=NPO・NGOで働きつづけやすい環境づくり~互助会ネットワークがめざしていること |
|
| 恒 例 の 師 走 事 業 |
| 市 民 4 5 人 が チ ャ レ ン ジ |
| 講師は美星の支援グループ |
師走恒例の正月しめ飾り作り方教室が12月21日、つどえ~るで開かれました。
講師は美星町の原田幸恵さん、鷹家勝己さん、片山恵さんの3人です。
会場には4枚のブルーシートが敷かれ、事前に申し込んだ45人はメガネ形しめ飾りとリース形しめ飾りの二班に分かれて座り、青田刈りをして用意された稲ワラなどを受け取って午前9時30分から作業を開始。
ワラを“撚る”ということがない現代人にとっては厄介な手順が待っているしめ縄づくり。どうやっても上手く行かない人たちは講師に手伝ってもらいながら仕上げていきました。
1時間もすると原形がほぼ出来上がり、飾りを取り付けて完成させました。
参加者はお互いのしめ飾りを見比べながら「思っていたよりきれいに出来ました。これで来年も良い年になると思います」などと笑顔で話し合っていました。 |
|
| クリスマスソング演奏♪ |
| 心 が 和 む チ ャ イ ム の 音 色 |
| つどえ~るへ50人集う |
師走にクリスマスソングを届けようとつどえ~るで12月20日、音楽療法で若返り教室がトーンチャイムコンサートを開きました。
開会にあたっての野宮弘恵代表(音楽療法士・歌唱療法士)は「多くの方にお集まりいただき有り難うございます。音楽療法で若返り教室は2021年4月、高齢者のための脳トレ目的で開講しました。その後、トーンチャイム教室も始まり、きょうはその皆さまに演奏発表をしていただきます。この活動に興味を持たれた方はお気軽にお声かけください」などと挨拶。
演奏は「聖者の行進」を皮切りに「ひいらぎかざろう」「冬景色」など9曲。会場を訪れた50人は約1時間、トーンチャイムの美しい音色を聴きながらクリスマス曲を歌い楽器を鳴らし、楽しいひとときを過ごしました。
様々な音楽イベントに出向いているという女性は閉会後「心が和む美しい音色には癒されますね」と感想を述べていました。
| 1 |
聖者の行進 |
| 2 |
ひいらぎかざろう |
| 3 |
冬 景 色 |
| 4 |
きよしこの夜 |
| 5 |
ジングルベル |
| 6 |
We wish you a Merry christmas
(合奏) |
| 7 |
トーンチャイム体験 |
| 8 |
Imagine |
| 9 |
ホワイトクリスマス |
|
|
|
| 防犯講演会を開催 |
| 坂田美春氏 忍び寄る犯罪に警鐘 |
| つ ど え ~ る 2 階 |
法務・教育・防災防犯の3分野で活動が著しいNPOあんしんの講演会が12月6日、つどえ~るで行われ約20人が受講しました。
この日の講師は同法人で防犯分野を担当している坂田美春氏(警察官OB及び行政書士)。
坂田氏は近年、闇バイト強盗や都会のマンションで刃物を持った男が面識のない人を殺害する事件が連続して発生していると指摘。井原市、笠岡市及び矢掛町の刑法犯認知件数を伝え、身近に潜む危険について警鐘を鳴らしました。
また、警察官になりすまし「お子様が逮捕されました。保釈金150万円を次の講座に振り込んでください」といった電話による巧妙な特殊詐欺にも注意を要すると呼び掛けました。
一方、防犯対策として敷地内に人などが侵入すると発光するセンサーライトや防犯カメラ、ガラスが割られるとブザーが鳴るような防犯グッズの活用を推奨。
さらに坂田氏は、軽い気持ちで1回でも使用すればやめられなくなる薬物(覚せい剤・大麻・麻薬)犯罪について、犯罪の温床となるので絶対に手を出してはいけないと強調しました。
閉会後、受講した一人は「さまざまな詐欺が身近なところに潜んでいますね。注意します」と話していました。 |
|
|
|
大相撲力士 手形 サイン 色紙展 |
|
|
|
|
|
2025/11/14 |
| 11月14日~同28日 |
| 北の湖や若貴兄弟ら手形など一堂に |
| 初の大相撲関係パネル展 |
横綱北の湖や千代の富士、若乃花貴乃花兄弟ら大相撲で活躍した力士の手形やサイン、色紙を集めた珍しいパネル展が11月14日、つどえ~るで始まりました。
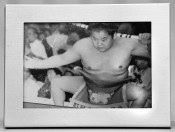
弓取式を行う幕下の秀の龍 |
|
|
このたびの展示はつどえ~る事務局の田原耕太郎さん(井原町倉掛)が約30年かけて集めた中の107点。
田原さんの二女が平成7年、元大相撲力士・秀の龍明彦氏(三保ヶ関部屋)と結婚したことがきっかけで、本場所観戦や手形、大相撲に関する資料などを集めるようになったものです。
田原さんは「展示品の多くは娘婿が相撲好きの私にプレゼントしてくれた品々です。現在11月場所が開かれていることもあり、この時期に展示させていただきました」と説明。
会場に訪れた人たちは「こういうのは見たことがありません。内閣総理大臣杯のレプリカは、秀の龍さんが同部屋の横綱北の湖から拝領したものと聞きビックリしました。珍しいお値打ち品の数々を見せていただき有り難うございました」と喜んでいました。
| 《 展 示 品 》 |
| 種類 |
数 |
種類 |
数 |
| 手 形 |
38 |
DVD |
20 |
| 欄間額 |
3 |
C D |
2 |
| 優勝杯レプリカ |
1 |
本 |
30 |
| 番付表 |
9 |
カレンダー |
1 |
| 写 真 |
2 |
入山番付表額 |
1 |
|
|
| 開 講 5 年 目 |
| 美 し い 音 色 に 参 加 者 笑 顔 |
| つどえ~る登録団体 |
トーンチャイムの演奏や歌を楽しむことで生活に潤いを与え、脳の活性化を図ろうと活動している音楽療法で若返り教室(つどえ~る登録団体)が11月9日、つどえ~るで無料公開講座を開きました。
冒頭、同教室を主宰している音楽療法士・歌唱療法士の野宮弘恵代表が、会場を訪れた約50人を前に「開講5年目になりました。きょうのイベントは教室関係者14人の発表の場であり、音楽療法が人々に活力を与えることを知っていただくための公開講座。童謡や懐かしい歌謡曲を一緒に楽しんでください」と挨拶。
体験はリラックス効果のある口で吐いて鼻から吸う呼吸法と、血流を良くするあいうべ体操からスタートし、歌の部門に入りました。最初の「ちいさい秋みつけた」では途中、指文字の手話を交える場面があり、思わず笑いが。
懐かしい歌謡曲合唱では昭和47年に流行った「学生街の喫茶店」、ペギー葉山が歌った「学生時代」、さらに「高校三年生」と続き、最後の「青春時代」では簡易楽器を鳴らし盛り上がりました。
発表演奏タイムでトーンチャイム受講者が「紅葉」「赤とんぼ」を奏でると、心地よい音色が響き渡り、館内は大きな拍手に包まれました。最後にトーンチャイムとベルを鳴らしながら「どんぐりころころ」を合唱し、90分の公開講座を終えました。
初めて公開講座に参加した60代の女性は「思い出深い歌謡曲や美しい音色に癒され、楽しいひとときを過ごせました」と話していました。 |
|
| 交通安全啓発パレード |
| 往時の井原鬼まつり堪能 |
| 2キロの道のり行進 |
井原町まちづくりの会(落合政満会長・つどえ~る登録団体)主催による鬼まつり交通安全啓発パレードが10月26日、井原町で実施されました。
行列は午後1時過ぎに向町を出発。素戔鳴尊命に扮した井原警察署長を先頭に鏡獅子太鼓や鬼の山車、町内から集まった鬼の集団らがこれらに続き、一行は同3時ごろ2km南の郷社足次山神社へ到着。
商店街筋では、内外から訪れた観光客やカメラマンが往時を偲ばせる光景を堪能していました
|
|
| 会期は10/18~10/31 |
| 歴史彩る20面&切り絵など展示 |
| つ ど え ~ る 1 階 |
備中神楽の彩りを伝える平川和夫神楽面作品展が10月18日、つどえ~る1階で始まりました。
面は昭和40年~50年代に近郷を舞台に神楽師として活躍した平川和夫氏が彫ったもので、息子の平川孝之さん(芳井町梶江)の所蔵品です。
4枚のパネルには神楽の演目で使われる20面などをはじめ、伝統芸能の歴史紹介や迫力ある孝之さんの切り絵(建御名方命舞い)も展示されており、祭りで賑わう井原の秋にピッタリ。
会期は10月30日(木)まで。見学無料。 |
|
|
|
第2回つどえ~るフリーマーケット |
|
|
|
|
|
2025/10/12 |
| 井原市民20店を開設 |
| 約300人の買い物客で賑わう |
| 施設の多目的機能発揮 |
第2回つどえ~るフリーマーケットが10月12日午前、井原市市民活動センターで開かれ約300人の客で賑わいました。
今回は井原市民限定20店がサツマイモ・ピーマン・カボチャ・ゴボウ・ナス・ジャガイモ・ブドウ・柿・クリといった野菜や果物をはじめ、手作りケーキやカレー・山菜おこわ・赤飯・おでんなどを販売。オープン(午前9時30分)と同時に館内は大賑わい。格安の衣料や日用雑貨、台所用品、スポーツ用品、ぬいぐるみ、古本、クラフトバッグのコーナーにも人だかりができました。
普段から会議などでつどえ~るを利用している男性は「きょうはいつもと違うつどえ~る。この施設は1階が広いので色々なことに使えますね」と赤羽根カフェで談笑。ジャムになるローゼルなどを販売した木之子町の女性二人は「次回もぜひ出店したい」と話していました。 |
|
| 10月12日(日)開催 |
| 出 展 者 募 集 を 開 始 |
| 出 店 料 は 無 料 |

秋のつどえ~るフリーマーケットは約20店が参加して10月12日(日)午前9時30分にオープンします。
賑わいの創出や施設の多目的利用を図ることを目的としており、今年3月実施したのに続き2回目の開催。多数の皆さまのお越しをお待ちしております。
出店募集要項はこちら |
|
| 非常ベル&館内放送使用 |
| 避難袋で2階から駐車場へ降下 |
| 湯沸し場からの出火を想定 |
不特定多数の人の出入りがある防火対象物に義務付けられている避難訓練が10月3日午後、つどえ~るで行われ約30人が参加しました。
この日は朝から小雨の降るあいにくの空模様でしたが、午後になっていったん止んだことから時間を早めて実施を決定、まずは警備会社への連絡です。
指定管理者のNPO法人市民交流ネットワーク井原の職員は打ち合せどおり、非常ベルを鳴らして模擬消火。館内放送で「火事です! 1階湯沸し場が燃えています。避難してください!」と呼び掛け、建物の中にいる人たちを安全な場所へ誘導しました。
卓球教室とJA岡山井原支部女性会の人たちは指示に従って屋外に出たり、2階に設置されている斜降式避難袋を使って北側駐車場へ滑り降りました。
笹賀町に住む60代の女性の一人は 「このような避難訓練は初めて。良い体験になりました」と話していました。 |
|
| 令和7年度前期 |
| 多目的利用さらに広がり |
| 6,845人が来館 |

(クリックで拡大します) |
つどえ~るの令和7年度前期利用者数は6,845人と、昨年度前期(6,250人)より9.5%増加しました。
施設の指定管理者であるNPO法人関係者は「新型コロナウイルスに対する警戒感はありますが、市民活動センターの多目的利用傾向は続いています」と分析。「引き続きつどえ~るが愛称どおり気軽に集える場と認識していただけるよう努めたい」と話しています。 |
|
| 人 物 写 生 会 |
| 女 性 バ イ オ リ ニ ス ト 描 く |
| メンバー15人が参加 |
つどえ~る登録団体の井原市文化協会洋画部(高橋朋子代表)が8月30日~31日の二日間、つどえ~るで人物写生会を開きました。
集まったメンバーは15人。それぞれお気に入りの角度からバイオリニストの女性モデルに向かい、写生はスタート。20分描いては10分休憩しながらキャンバスへ筆を走らせました。 |
|
|
|
つどえ~る手話体験講座(2回目) |
|
|
|
|
|
2025/7/26 |
| 2 8 人 が 参 加 |
| 単語を組み合わせて手話表現 |
| 通算24回目の開催 |
本年度2回目の手話体験講座(主催=井原市聴覚障害者協会及びつどえ~る)が7月26日、井原手話サークルの協力を得て開かれ28人が受講しました。
講師は前回と同じ鳥越裕子氏と堀之内まい氏。冒頭、鳥越氏は「近年はインターホンが鳴ったりFAXが入ると、光でそれを伝える機器などができて徐々に便利になってきています。しかし、町なかで道を尋ねられても聞こえないので答えてあげることができない、といった不自由さが日常生活に存在します」と述べ、「手話が言語として広がることを願っています」と皆に伝えました。
このたびは6月の講座に参加できなかった人が、自分の名前を手話でどう表現するか教わることからスタートしました。続いて、つどえ~る・勉強・一緒に・行く・ちょっと・待つ・この前・習う・頑張る・暑い・台風・雨・晴れといったよく使う単語などの手話を習いました。
これらの文言を使って隣の人と「こんにちは。つどえ~るへ手話の勉強に一緒に行こう」、「すごい雨だった。きょうは晴れてよかったね」、「また会いましょう。バイバイ」などの会話を手話で行ってみました。
今回も楽しい90分間を過ごし、10数人は閉会後もしばらくつどえ~るで復習していました。 |
|
| 作 品 に 奥 深 さ |
| 1 0 人 の 力 作 一 堂 に |
| 集 中 力 と 根 気 表 現 |
切り絵の魅力を伝えたいと、つどえ~るで7月10日より、きりえアートの会(平川孝之代表)の展示会が始まりました。集中力と根気で仕上げた10点は力作ぞろい。皆さまのご来場をお待ちしております。
会期は7月27日まで。7月21日と22日は休館。
|
| 《 出 展 者 》 |
| 井上 文秀 |
山下 榮一 |
| 妹尾 好江 |
田中 久子 |
| 木山 節子 |
三宅紀美子 |
| 三宅 好江 |
中新 暢子 |
| 樫原美智子 |
平川 孝之 |
|
| C O 2 削 減 P R |
| 緑 の カ ー テ ン 鮮 や か |
| 道 行 く 人 た ち の 目 引 く |
国連が定めた開発目標SDGs13番目「気候変動に具体的な対策を」に呼応し、CO2削減運動を推進しているつどえ~る。
ツル性植物の緑のカーテンで強い日差しを遮ろうと4月13日、井原高校精研農場で育ったゴーヤの苗600鉢を井原市民100人(一人6鉢)へ無料配布しました。
約3カ月でつどえ~る西側と南側の苗はどちらも窓の高さまで伸び、室内温度上昇を抑えるとともに道行く人たちの目を引いています。 |
|
| お部屋でバードウオッチングⅢ |
| 特別天然記念物 「コウノトリを知ろう」 |
| 30人がつどえ~るで学習 |
井原野鳥倶楽部(藤井聖三代表・会員15人)主催の野鳥セミナーが7月15日、つどえ~るで開催され市内外の野鳥ファンらが訪れました。
同倶楽部は令和5年に発足し、井原市制70周年記念事業の市の鳥(メジロ)制定に貢献したつどえ~る登録団体。定期的に屋外でのバードウオッチングや一般市民向けの野鳥勉強会を開くなど、活動の場を広げています。
この日は「特別天然記念物・コウノトリを知ろう」と題した内容で、参加した30人にコウノトリの特徴や不思議な鳥の生態について、配布資料やスライドを使い約90分、藤井代表が説明しました。
受講者らは、井原市へ飛来した大山町生まれのコウノトリが今年3月、上稲木町で交通事故に遭ったことや、足環の色や番号を確認することで孵化年月日・孵化場所・巣立ち年月日・親鳥などが分かる個体検索システムには高い関心を示していました。 |
|
| 特別天然記念物 |
| 市内で撮影の写真を展示 |
| 7月3日にセミナー |
井原野鳥倶楽部(藤井聖三代表・つどえ~る登録団体)が6月28日、特別天然記念物コウノトリの写真6枚を展示しました。
7月5日に開催するお部屋でバードウオッチングⅢコウノトリセミナーの事前PRの一環で、井原市内で同倶楽部のメンバーが撮影したもの。
写真に写っている足環の番号等を確認することで、生まれた日時や場所を特定できるようにコウノトリ最後の生息地・兵庫県豊岡市が取り組んでいます。
コウノトリ個体検索 |
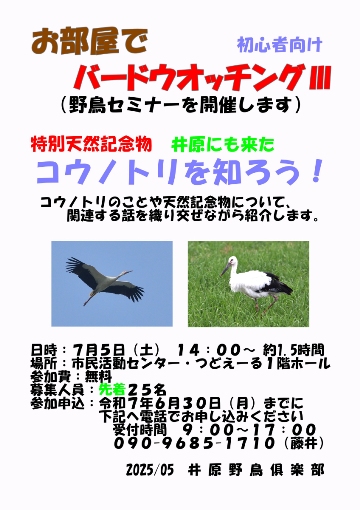
(拡大します)
|
|
|
井原市がんばる地域応援補助金審査会 |
|
|
|
|
|
2025/6/17 |
| 3団体がプレゼン |
| 審査委員 事業目的などただす |
| つどえ~るで開催 |
令和7年度井原市がんばる地域応援補助金審査会(第2回)が6月17日午後、つどえ~るで開かれました。
申請団体ごとに井原市市民活動推進課の岩本陽子課長が発表や質疑時間などの流れを伝え、プレゼンテーションに入りました。
木之子地区振興協議会など3団体はそれぞれ一つの事業を3分以内で説明。続いて審査委員長の米良重徳氏(岡山NPOセンター)をはじめ、岡本聡氏(備中県民局)、小川孝雄氏(美作大学講師)、高平亮氏(岡山NPOセンター)、田辺義博氏(moko’a統括)が事業目的や将来的見通しなどについて質問し、申請者側がこれに応える形で行われました。審査結果については後日、文書で回答されます。
|
|
➀ |
木之子地区振興協議会 |
6事業 |
|
➁ |
県の里まちづくり推進協議会
|
3事業 |
|
③ |
野上地区まちづくり協議会
|
3事業 |
|
|
|
|
|
| 実用的作品28点 |
| 色彩やデザイン鮮やか |
| つどえ~るへ展示 |
井原クラフト会(小倉好恵代表)がつどえ~るで6月8日より、ハンドメイドのクラフトバッグ展を開いています。
玄関を入ると目に飛び込むのはメンバーが趣向を凝らした色彩豊かな近作28点。4枚のパネルへ掛けられ、館内に明るい雰囲気を映し出しています。来館者の中には「えーっ、これを自分で仕上げられたんですか?」と驚く人も…。
関係者は「お時間がございましたら是非ごお立ち寄りください」と話しています。
(会期:6/8~6/27) |
|
|
|
つどえ~る手話体験講座(1回目) |
|
|
|
|
|
2025/6/7 |
| 2 8 人 が 参 加 |
| 講師に鳥越氏&堀之内氏招く |
| 通算23回目の開催 |
井原市聴覚障害者協会と井原手話サークルの協力を得て6月7日、つどえ~る手話体験講座が開かれ28人が参加しました。
今回の講師は鳥越裕子氏と堀之内まい氏の二人。最初は鳥越氏が口話学習が主流だった頃から今日の手話に至る経緯等について説明。続いて「おはよう」「こんにちは」などの挨拶や「そうそう」「覚えた」「忘れた」「また会いましょう」といった日常会話を手話でどのように表現するか皆で復習しました。
休憩後は自己紹介の仕方、参加者全員の苗字の表し方を学習。地域に多い苗字はその土地でのみ通用する特別な手話があることも教わりました。
後半には二人一組で挨拶をかねた会話にもチャレンジするなど、笑い声が絶えない90分間を過ごし、午後3時に閉会。次回は7月26日に行われます。
この日の講座に参加した女性の一人は「知らないことを習うのは面白いですね」と話していました。 |
|
| 無 料 公 開 講 座 |
| 出演者と観客 共に講座楽しむ |
| つどえ~る登録団体 |
音楽療法で若返り教室(野宮弘恵代表・会員40人)がつどえ~るで5月31日、無料公開講座を開催し52人が参加しました。
冒頭、開会挨拶で野宮代表は令和3年、認知症予防などを目標に立ち上げた若返り教室の活動内容を紹介。普段はつどえ~るや高屋公民館で歌やトーンチャイムの演奏を楽しんでおり「多くの人たちが音楽を健康づくりに役立ててほしい」と企画したものです。
プログラム1番は口や舌の筋肉を鍛え、誤嚥防止につながると言われているパタカラ体操を「みかんの花咲く丘」の曲に合わせて歌唱。続いて童謡唱歌「夏は来ぬ」や「南国土佐を後にして」、「上を向いて歩こう」など、かつてヒットした歌謡曲を歌ったり、歌体操や手作りマラカスで合奏したりしました。
教室の人たちによる「荒城の月」と「浜辺の歌」の演奏では、心地よい澄んだ音色が響き渡り、館内は大きな拍手に包まれました。
最後に演奏体験が行われ、訪れた人たちも、実際にトーンチャイムで唱歌「茶摘」の演奏に加わり、盛り上がりました。
このたびの公開講座に初参加した女性の一人は「多くの皆さんと共に楽しいひと時を過ごせて良かった」と感想を述べていました。 |
|
| 井原市民ギャラリーで開催 |
| 会員18人の力作41点を展示 |
| つどえ~る登録団体 |
つどえ~る登録団体の井原市文化協会洋画部(妹尾均部長)が令和7年度洋画部展を5月21日~25日、井原市民ギャラリー(平櫛田中美術館)1階)で開催しました。
このたびは会員18人の力作41点を展示。観賞に訪れた人たちは個性溢れる油彩・水彩などをゆっくり楽しんでいました。出品者目録
|
|
| 空き家アドバイザー |
| 活性化対策へチャレンジ |
| 県内外から20人参加 |
人口減少に伴う空き家対策へ向けて活動している(一社)全国空き家アドバイザー協議会・岡山県井原支部の井原市未来創生会議が5月9日、つどえ~るで開かれ県内外の関係者20人が出席しました。
会議は国土交通省が推進している二地区居住の内容説明等を中心に、井原支部における今後の展開を模索する方向で行われました。
次回開催は6月13日の予定。
|
|
| 井原市芳井町簗瀬へ |
| 23人参加 「歩いて歴史学習」 |
| 新 緑 ゾ ー ン 満 喫 |
第11回つどえ~る健康ウォーク(井原まち歩きの会・つどえ~る共催)が4月21日、好天の下で実施され、23人が参加しました。
一行は午前9時50分、井原市芳井町簗瀬の桜渓塾に到着。当時の塾を偲びつつ、興譲館初代館長阪谷朗盧と渋沢栄一の関わりを学びました。
少し下ったところにある妙善寺に立ち寄り集合写真をパチリ。そこから15分も歩くと急坂が続く青龍神社。十輪院では、寺の歴史や仏教用語「代受苦」などについて教わり、参加者の多くが納経帳へ御朱印をいただきました。
さらに10分ほど歩くと文化元年創業の山成酒造へ。令和6年3月、国の登録有形文化財となった店舗兼主屋や酒蔵、離れ座敷や山成家についての説明に耳を傾けました。
近くの緒方研堂旧宅前では、井原まち歩きの会の森昭二前会長が研堂について詳解。葉桜が美しい小田川土手下で昼食をとりながら休憩し、再び桜谷公園に戻って約4㎞の健康ウォークを終えました。
毎年参加している西江原町の男性は「歩く距離こそ短かったが、きょうは随分と歴史の勉強をさせてもらった」と笑顔で話していました。 |
|
| 井原高校精研農場の苗 |
| つどえ~るで600鉢を無料配布 |
| 緑 の カ ー テ ン 推 奨 |
国連が定めた持続可能な開発目標SDGs。つどえ~るではその13番目の「気候変動に具体的な対策を」に呼応して、環境に優しい植物を育てる運動を推進しています。
その一環として、井原高校精研農場で育ったゴーヤの苗600鉢を井原市民100人へ無料配布。“緑のカーテン”で強い日差しを遮り、二酸化炭素(CO2)排出量を削減する省エネ運動を目指そうと2021年から行っています。
事前に申し込んだ井原市民100人の引取りは4月13日午後1時30分から始まり、ゴーヤ6鉢入りの袋と栽培の手引を手渡しました。
つどえ~る関係者は「愛情をもって育てていただきたい」と話しています。 |
|
| 井原桜まつり賑わう |
| 満 開 の 桜 花 見 客 満 喫 |
| 井原町まちづくりの会 |
井原町まちづくりの会(落合政満会長・つどえ~る登録団体)主催の井原桜まつりが4月6日、好天の下で開かれ内外から訪れた花見客で賑わいました。
例年、桜の開花情報に気をもむ行事ですが、今年は見事に満開。午前8時45分、井原公民館からスタートしたウォーキング参加者が約1時間ほどで桜橋公園に到着すると、道中おどり一行も井原音頭などの曲に乗って会場入り。祭りに花を添えました。
開会にあたり、落合会長が祭りの運営に関わっている人たちへ謝意を表し、続いて来賓の加藤勝信財務大臣や大舌勲市長、上田勝義県議が「井原の桜と華やかなイベントをみんなで楽しんでください」と祝辞を述べました。
午前10時20分、勇壮な和太鼓でオープニングを飾り、井原中学校吹奏楽部・アマチュアバンド・エレクトーンの演奏、太極拳・子ども神楽・傘おどり・銭太鼓などが次々と披露され会場を盛り上げました。 |
|
| 団体活動は横ばい |
| 施設利用は前年比4.7%微増 |
| つどえ~る年間集計 |
つどえ~るの2024年度(令和6年度)年間利用者数は13249人(前期6250人・後期6999人)と対前年比で約4.7%の微増でした。
施設利用は多岐にわたっているものの登録団体等の活動は依然、横ばい傾向にあります。
|
|
|
 |
Library & Download |
|
|
